本学科の概要

本課程は2007年(平成19年)からスタートしている「特別支援教育」の専門家である特別支援学校教員を養成する課程です。特別支援教育は、これまでの養護学校や特別支援学級、通級指導教室(ことばの教室や情緒障害の教室)に加えて、通常の学級に在籍する学習障害(LD)や注意欠陥/多動性障害(ADHD)、高機能自閉症などの障害のある子ども達にも積極的に対応するものです。
本課程も平成20年度より、これまでの養護学校教員養成課程から特別支援学校教員養成課程(定員20名)へと名称を変更し、特別支援教育の理念をより具現化するための専門性の高い教員養成を行っています。本課程では特別支援学校(これまでの盲・聾・養護学校)の教員だけでなく、小学校の教員になったときに役に立つ特別支援教育の専門的知識や技能を習得できます。また小学校課程に入学して副専攻として特別支援教育を専攻する学生についても受け入れています(定員3名)
取得免許

特別支援学校教員養成課程では、小学校教諭1種免許(基礎免)と特別支援学校教諭1種免許(知的障害、肢体不自由、病弱)を取得することができます。さらに本人の努力が必要ですが幼稚園1種免許を合わせて取得する学生もいます。
基礎免許として小学校教諭1種免許の代わりに中学校1種免許を取得することもカリキュラム上は可能ですが、本人の多大な努力が必要です。また小学校教諭1種と特別支援学校教諭1種免許を取得する場合、中学校教諭1種免許を合わせてとることはできません(中学校教育実習に参加できません)。ただし本課程を卒業後、特別専攻科専修コースに進学して、中学校教育実習に参加し、学部在籍時に取得した単位と合わせて中学校教諭免許を取得することは可能です。
学生生活

多くの学生が障害のある子ども達に関わるボランティア・サークルや夏休みなどの長期休暇中に療育キャンプに参加しています。特別支援学校教員養成課程では、実際に障害のある子ども達と関わる機会に恵まれており、自閉症研究会やダウン症研究会などのボランティア・サークルへの参加を薦めています。これ以外にも、教員を中心とした重複障害研究会や動作法研究会、学習支援教室などの研究会もあります。
カリキュラム
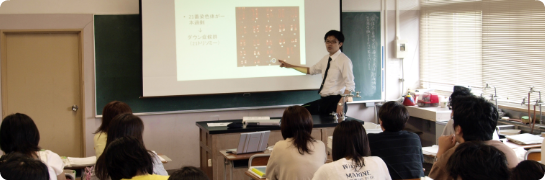
授業では、基礎的な知識を習得することに加えて、教員になった時にすぐに対応できることを目指して、教材教具の開発、行動分析学、臨床動作法などの実践力を養成するための演習が組まれています。さらに、3年生からはそれぞれの指導教員の指導の下で卒業論文の作成に向けた研究が始まります。また、3年生の後期に附属特別支援学校での教育実習と附属小学校での教育実習が行われています。
卒業後の主な進路
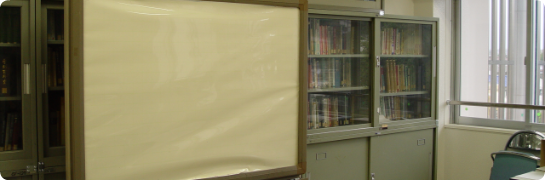
本課程の卒業生の多くは、特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室などで働いています。さらに小学校の教員として働いている人も多く、本課程で得られた知識や技能は、通常の小学校の学級担任になる上でもとても役に立つものです。また、学生の中には卒業論文研究を通じて研究に興味を示し、大学院に進学する学生も多いのが特徴です(卒業生のうち約3割が大学院や専攻科などへ進学します)。進学先は熊本大学だけでなく、筑波大学、東京大学、九州大学などの研究者養成への道を進む人もいます。

